以下はあたくしの実習中の本当にあった残念なエピソードです。
ROM測定は痛い思い出しかございません。涙
実際に患者さんでROM測定を行ってみました。
でも、ゴニオが動いてしまい、目盛りを読み、角度を出すのにとても時間がかかってしまいまいました。
また患者さんにゴニオを強く押し当てたため、患者さんに痛い思いをさせてしまいました。
自分はバイザーから冷たい視線を浴び痛い思いをしました。
事前にマスターしておくと、役に立つことを以下に挙げてみました。いやー、ホンとに、自分が実習生の時に知りたかったです
尋常でなく緊張する、患者さんを被検者としたROM測定。
少しでも本番でドギマギしたくない。そんなあなたは必読です。
- ゴニオメーターの扱いに慣れておきましょう
- 骨指標などのランドマークを確実に触診できるようにしておきましょう
- 最終域はバイザーに確認しましょう。
上記を実践し、少しでもスムーズな測定を行ってくださいね。
ゴニオメーターの扱いに慣れておきましょう。
ゴニオメーターは開いた状態でセットして置(お)こう
予め参考可動域に開いて置いておきます。
測定姿位を確定させた後、開いておいたゴニオメーターを目盛りが動かないよう持って測定します。
ゴニオメーターの持ち方を知っておこう
写真つきの詳しいサイトもあります。そちらを参考にしてください。
ゴニオメーターの目盛りを読む前、後にもう一度基本軸、移動軸が合っているか確認しましょう。
測定している時は、ガチガチに緊張し、肩の力が入っている状態であることは仕方がない事です。。
そのような状態ではゴニオメーターは、はじめに自分が設定したポイントから、ずれていることがほとんどです。
ですから、測定姿位を確定させ、目盛りを読む前に、ちらっとでも良いので基本軸、移動軸の位置を目視して確認しましょう。ずれていたら修正しましょう。
骨指標、ランドマークは確実に触診できるようにしておきましょう。
基本軸と移動軸を同定するためには、骨指標などの、ランドマークの正確な位置を知っている必要があります。
上肢の場合は肩関節の肩峰の位置、下肢では大腿骨の大転子など、頻出部位は実習前にしっかりと触診できるようにしておきましょう。
骨指標が誤っている→基本軸が間違っている→バイザーが測定した角度と異なった角度で判定してしまう。という結果になりがちです。
第7頸椎棘突起の触診の仕方
- 頸部は中間位です。
- 背部からみて首の中央と体幹が交わる付近を指で触ります、
- 棘突起を触知できますが、その中で1番目と2番に出っぱってる部分を示指、中指で触ります。
- 頸部を左右に回旋させた時に、動きを感じるのが、第七頸椎棘突起です。動きが感じられないのが、第1胸椎棘突起です。
文章のとおりやってみてください。そんなに難しくないですよ。
肩峰の触診の仕方
- 上腕骨と肩の境目の辺りを、自分の指で触ります。
- 肘を90度屈曲させた姿勢で、肩関節を内外旋させます。
- その時に動きを感じる部分が上腕骨で、動きを感じない部分が肩峰です。
最終域まで関節を動かしているか、その都度バイザーに確認しよう。
自分が測定して出した値と、バイザーが測定した値が異なる理由の一つに、「最終域まで達していないところで測定している」ことがあげられます。
エンドフィールを意識しながら、最終域まで動かしていく必要がありますが、実習生にとって、そう簡単なことではありません。
最終域を意識するあまり、患者さんの体を力ずくで押し込んでしまう!なんてことは、あってはなりません。
ここは素直に、自分が最終域であると判断した時点でバイザーに本当に最終域であるか、フィードバックしてもらいましょう。
バイザーに、たくさんフィードバックしてもらい、最終域の判断の仕方を体感する機会を多く持つことが大事です。
まとめ
実際に患者さんにゴニオを当ててみると、ほとんどの実習生はバイザーの様にスムーズに測定できないかと思います。
その都度バイザーが、改善すべき点を指摘し、実習生は修正しながら測定していきます。
同じことを何度も何度も指摘されてしまうこともあるでしょう。。しかしそれが普通です。落ち込む必要はございません。
この記事をよく読んで、しっかりと事前の準備をすれば、きっとバイザーも、あなたのがんばりを評価してくれることでしょう。
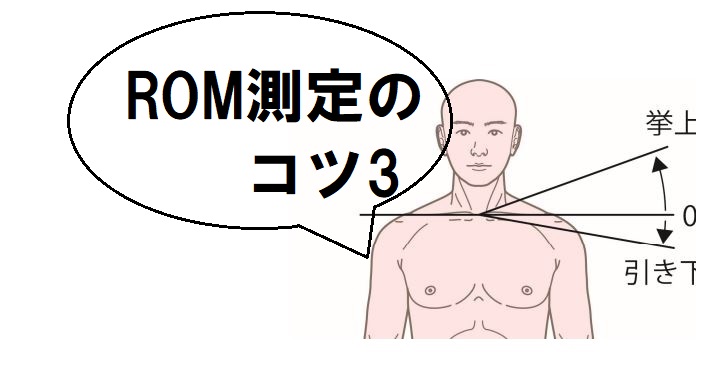

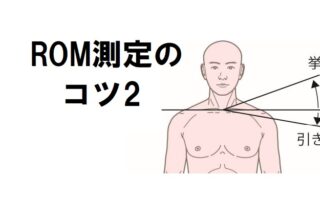
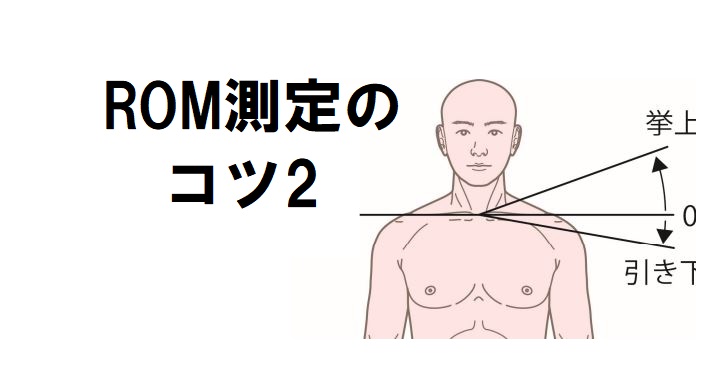
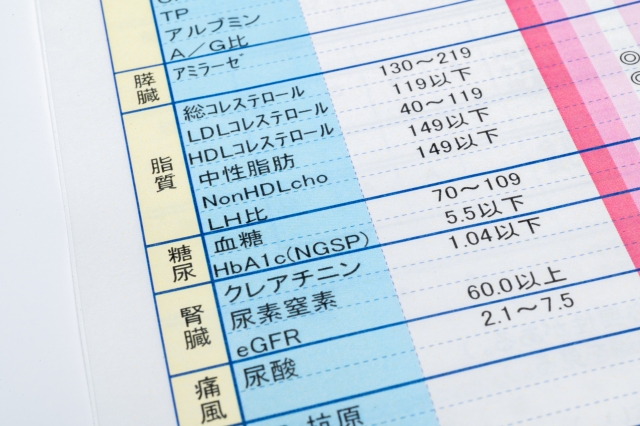
コメント