
入院患者さんが、自宅に戻れる条件として、一番あがるADL動作は何?

やっぱ、トイレ動作が自立できるか?かな?

そうだよね。自分でトイレに行けなくて、オムツの後始末を家族が行うことは大変だものね。。

じゃあ、トイレ動作自立のために、重要な要因て何?

今日は”作業療法士”の日頃の臨床の成果が詰まっている、「全国学会」の演題をみながら、説明していくよ。
- トイレ動作を自立に導くためにはどのような点に着目すればいいの?
- トイレ動作自立のための、評価スケール、方法を知りたい。
- 今の作業療法のトイレ動作自立のための考え方のトレンドをしりたい。
そんな皆様におススメでです。
トイレ動作自立の鍵は“高次脳機能”と”下肢(バランス)”の機能。
毎年1回行われる作業療法士の全国学会である「日本作業療法学会」の発表に目を通してみました。
今の作業療法の最高レベルの知見が集まっていると言っても過言ではない(ちょっと大げさ?)この学会の演題の抄録を読んで分かったことは
トイレ動作自立の鍵となる要因は バランス機能 と高次脳機能にあるということでした。
最近のトイレ自立に関連する演題名と、その内容について簡単にみていきましょう。
2021年 仙台 開催の演題より
「バランス能力と高次脳機能が脳卒中後のトイレ動作自立に及ぼす影響について」
そのままズバリなタイトルです。https://www.jaot.net/proceeding/2021/pdf/endai100664.pdf
2019年 福岡 開催の演題より
「急性期脳梗塞患者のトイレ動作自立となる要因分析」
https://www.jaot.net/proceeding/2019/pdf/endai100596.pdf
- ブルンストロームステージの下肢の機能
- TCT(体幹機能テスト) のスコア
- MMSEの点数
以上をトイレ動作自立のための要因としてあげていました。
2018年 名古屋 開催の演題より
「回復期リハビリテーション病棟に入院した患者におけるトイレ使用自立の予後予測」
https://www.jaot.net/proceeding/2018/pdf/endai100079.pdf
- FIMの認知項目(カットオフ値は19点)
- 握力
- 膝伸展筋力
- FBS(ファンクショナルバランススケール)
以上をトイレ動作自立に深くかかわる評価項目としてあげていました。
ちなみ12年前の演題では「高次脳機能」が問題という認識はありましたが、ではどのように高次脳機能を評価していたか?という具体的な評価方法は記載されていませんでした。
以下をご覧ください。
2010年の宮城(仙台表記ではありませんでした。)開催の演題は
「脳血管疾患患者がトイレ動作・移乗監視以上で自宅退院出来なかった要因」
→https://www.jaot.net/proceeding/2010/pdf/endai100504.pdf
「下肢のBRSの程度」と「高次脳機能障害の有無」について述べられていました。
その後の全国学会では高次脳機能の具体的な評価指標が表されるようになってきました。
非麻痺側上肢機能はどうなの?
OTとしては関心が高い「上肢機能」は、トイレ動作の自立にかかわる評価項目として、優先順位は高くなく、触れられている演題は多くありませんでした。
トイレ動作の自立を目指した訓練をしているOTの方にとっては、当たり前と言っては当たり前の結果、実際に訓練を行っている時の実感に近い結果ではないのでしょうか?
また、認知や高次脳機能の面では HDSーRではなく、MMSEを使って評価した方が、自立予測においては正確であるとの文献が多かったです。
HDS-Rは即時記憶や言語的記憶の項目が多いです。
MMSEは実際に図形を描いたり、道具を使用した動作指示の課題があります。構成能力や遂行機能を評価することできます。
このあたりがHDS-Rではなく、MMSEが選ばれている要因なのかもしれません。
なぜバランスと高次脳機能が重要なのか?
多くの文献でトイレ動作の自立を阻む最も関係の深い要因として、
「ズボンの上げ下ろし」の工程を挙げています。
文献によって違いはありますが、上げる時よりも、「下げる時」の方がバランスを崩しやすいと している文献の方が多いです。
ズボンを上げ下ろしをする時は、非麻痺側を手すり等を把持し、体を支えるために使用するのではなく、ズボンの操作に使用しなくてはなりません。
当然バランス機能の低下した片麻痺者にとっては、転倒のリスクが高い動作となります。
また、自身のバランス戦略が破綻していないかを正しく認識するための、高次の脳機能が維持されていることもトイレ動作自立のためには必要です。
バランス機能の評価について
ではバランス機能のをどのように評価しているのでしょうか?比較的容易と考えられる方法としては、
1.初回介入時の端坐位保持能力
「急性期脳卒中患者のリハビリ開始時の座位能力からみるトイレ動作の予後について」
→https://www.jaot.net/proceeding/2010/pdf/endai100611.pdf
この論文は2010年の宮城の全国学会で発表されました。
結論は 脳卒中の急性期の患者さんは、
介入開始時に端坐位保持能力があれば、その80%の患者が、最終的にトイレ動作自立に至った
というものです。
演者は急性期病院に勤務しており、介入した患者さんの多くは回復期リハ病院に転院します。
回復期に転院した患者さんの、その後のADLの自立したかを、追跡調査したものです。
急性期のOTにとっては手軽に評価可能なので、実施する価値は高そうですね。
ただ、この演題以外は、端坐位保持の可否を予後予測として使っている文献はみあたりませんでした。
2.TCT(トランクコントロールテスト)
- 所要時間は5分程度で方法も比較的容易。
- ベッド上でできる体幹機能の評価です。寝返りから起き上がり、端坐位までを評価します。
- 歩行との関連性が高い
3.バーグバランススケール(Berg Balance Scale:BBS)
- 所要時間は15分程度
- 対象は平衡感覚に障害のある高齢者、脳梗塞の患者です。
- 多くの作業療法学会の演題でで採用されていたバランススケールです。
あらかじめ決められた一連の作業において、患者さんが安全にバランスをとることができる能力(またはできない能力)を客観的に判断するために使用されます。
各項目は0から4までの5段階評価で、0が最低レベル、4が最高レベルの機能を示し、14項目のリストで評価します。
参考→http://daybook.jp/image/download_sozai/201912/201912-6.pdf
その他
- FRT(ファンクショナルリーチテスト)
脳卒中片麻痺患者の場合は、「15cm未満」で転倒リスクが高いと言われています。 - FBS(ファンクショナルバランススケール)
- FACT(ファクト) 臨床的体幹機能検査
- 麻痺側荷重テスト
などが採用されていました。
高次脳機能はどのように評価しているのか?(容易な順番から)
1.MMSE
HDS-Rよりも、MMSEの評価の方が、トイレ動作の自立に関する因子としての関連性が高いという論文が多いです。
ただし、高次脳機能の評価バッテリーとして、HDS-Rが採用されている論文もあり、その場合はHDS-Rの相関性も高いと結論づけられている演題もあります。
2.FIM-C FIMの認知項目
リハビリ職、特にOTにとっては、お馴染みのADL評価スケールですね。
FIMの総合得点から自立の予測をする文献もありますが、高次脳機能の評価に着目すると、FIMの認知項目のみを評価対象として抽出していました。
カットオフは19点とされている文献がありました。
3.CBA(認知関連行動アセスメント)
勉強不足でして、はじめて知った評価方法です。方法も複雑ではなく、臨床場面で使いやすい評価方法だなと思いました。
https://www.cba-ninchikanrenkoudou.com/_files/ugd/a7e5c9_8fb46ce3b5b145a0a85090ba857b5ae3.pdf
学会の論文の中で採用されていた高次脳機能評価は上記の3つが多かったです。
まとめ
- トイレ動作自立の鍵は下肢機能を中心とした バランス機能と 高次脳機能
- また介入初期の段階で、ある程度トイレ動作の自立予測も可能です。
- 積極的に文献を読みこみましょう。
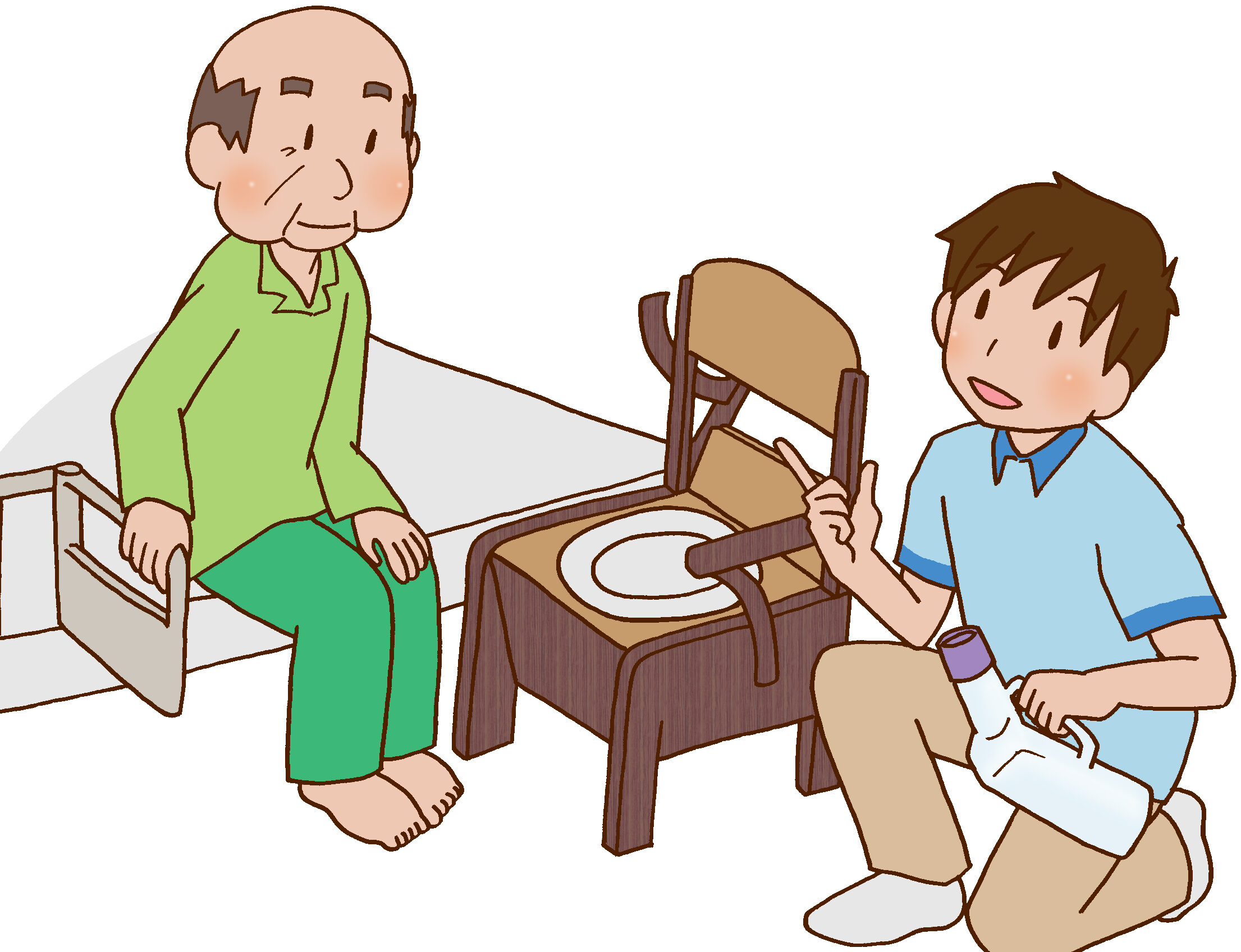
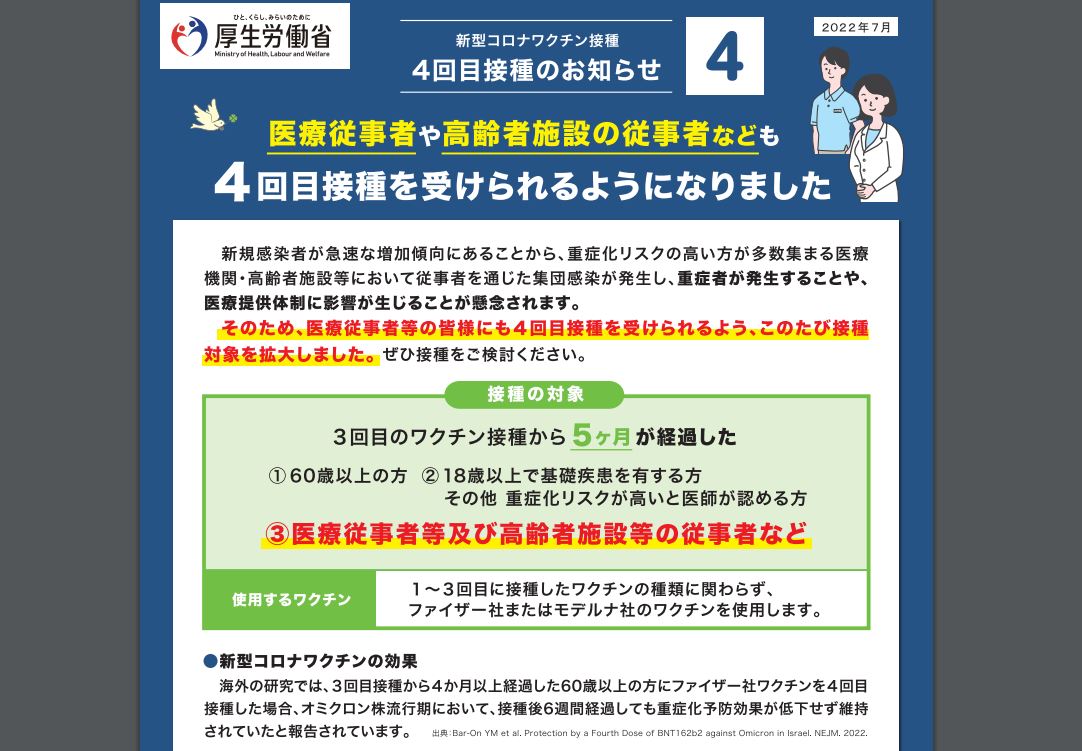

コメント